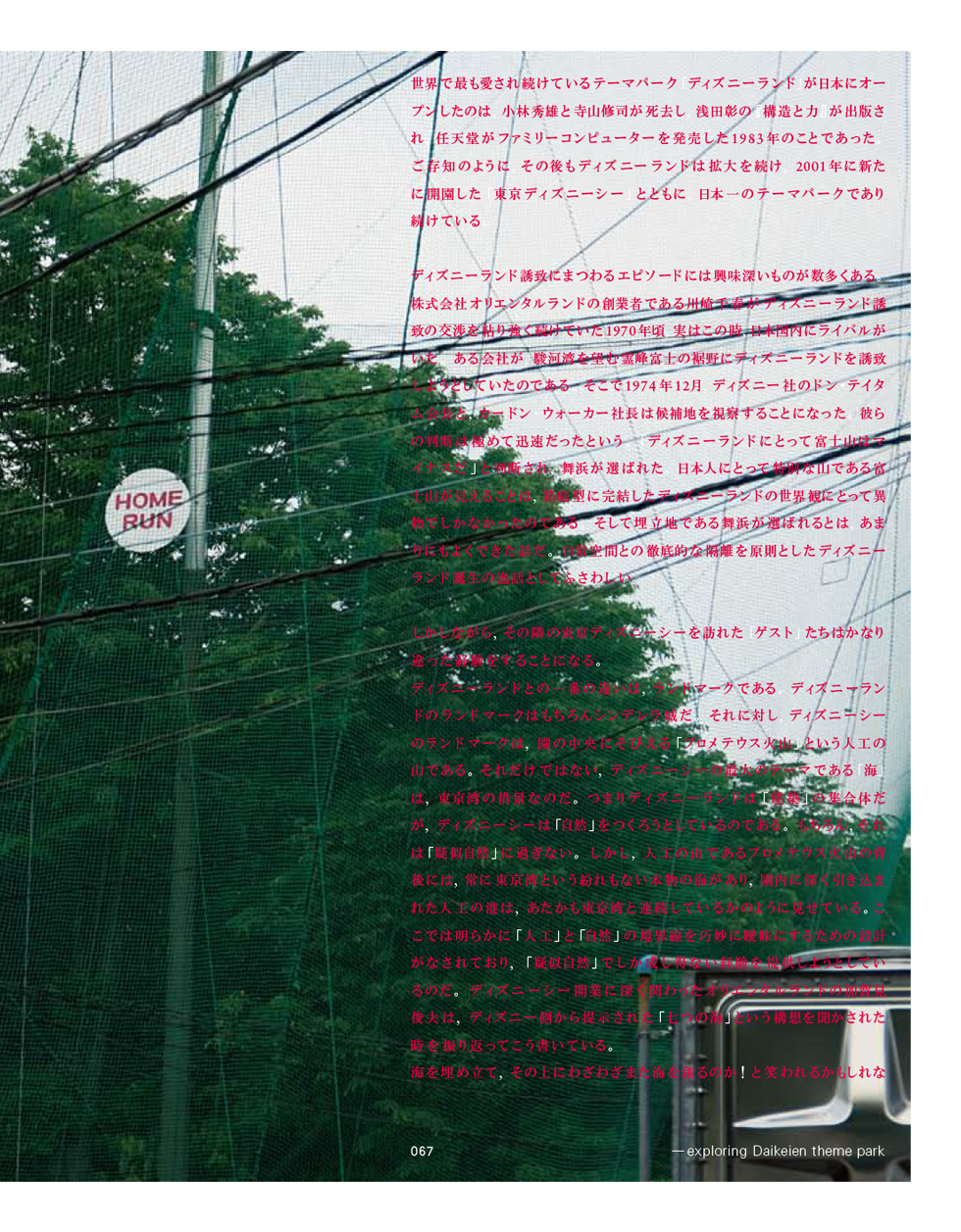日本がアートにおいて「受け入れ」の大国である、と謳ったのは言うまでもなく岡倉天心である。古美術調査のために一年間滞在していたインドで執筆された英文著書 “The Ideals of the East ”(『東洋の理想』)のなかで天心は、「アジア」と名指される広大な領域を行き交う様々な文化を指し示した上で(「理想」を “Ideals” と複数形で表記しているのはそのためである)、それらすべてが流れ込み、失われることなく保存されている特権的な場所として日本を位置づけている。このような天心の美術史観は、有名な「日本はアジア文明の博物館」という言葉によく表れているとされている。
しかし同時に、その言葉の直後に以下のような文章が続いていることを見逃すわけにはいかない。
いや博物館以上のものである。なんとなれば、この民族のふしぎな天性は、この民族をして、古いものを失うことなしに新しいものを歓迎する生ける不二元論[アドヴァイティズム]の精神をもって、過去の諸理想のすべての面に意を留めさせているからである。(岡倉天心『東洋の理想』講談社学術文庫より)
日本はアジア文明の宝物の数々を単に所蔵しているだけでなく、その上から不二元論の精神をもって新しいものが受け入れられ、そして受け入れられたものたちには過去の諸理想が宿る……
「日本の芸術の歴史は、かくして、アジアの諸理想の歴史となる――相ついで寄せてきた東方の思想の波のおのおのが、国民的意識にぶつかって砂に波跡を残していった浜辺となるのである。」
なんと壮大で「理想」的なヴィジョンであろうか。
天心の言葉とともにアジア文明を見渡すならば、現在のぼくたちでさえ「アラビアの騎士道、ペルシアの詩歌、中国の倫理、インドの思想」といったものたちに対して、少なからぬ親しみと当事者性を持って思いを馳せることができるだろう。広いアジアの端の小さな島国である日本にとって、「受け入れ」の国であるという自意識は長い間、他国との関係性をモデリングし、文化形成の指針であり続けていたはずである。
しかしながら、同時にこうも思う。
果たして今日のぼくたちは、「博物館以上のもの」としての日本文化のあり方を、ヴィジョンを、どこまで現実的に想像することができるだろうか、と。そして、今日のアートには、一体どれほど「生ける不二元論の精神」が通っているだろうか、と。
もちろん、天心の生きた時代に理想的な文化や作品が花開いていた、というわけではないだろう。だからこそ天心は『東洋の理想』のような、マニフェストとしての美術史を語ったのだろうし、横山大観や菱田春草といった弟子たちに、自らの理想とする絵画を実践させようと腐心したのだろう。
しかし、それにしても、である。今日のぼくたちにとってアジアは遠く、天心が謳いあげたような「受け入れ」大国としての日本の姿は、もうずいぶんと長い間、潜在的なレベルに留まり続けているのではないだろうか。たとえば現在、国内で「受け入れ」という言葉を出したなら、真っ先に連想されるのは「瓦礫受け入れ問題」や「移民受け入れ問題」といった「問題」の数々なのだ。
ぼくたちは今一度、「受け入れ」という語本来のポジティブな意味を取り戻し、アジアにおける「受け入れ」の国としてのヴィジョンを描くべきなのではないか。そのために、アートの力が必要なのではないか。
こんなことを考えて本誌を編みはじめることになったのには、ひとつの大きなきっかけがあった。
それは、アーティスト・村上隆が震災後、カタールで開催した『Murakami - Ego』展である。詳細を記すなら、2012年2月7日、『Murakami - Ego』展オープニング前日のインターネット生中継で、新作として出展されていた巨大な絵画《五百羅漢図》をモニター越しに見た時から、である。震災への応答として描かれた《五百羅漢図》は、これまでのすべての村上隆作品が総合されたようでありながら、しかし「オタク」も「スーパーフラット」も超えた、現代の巨大な仏教芸術とでも言うべき絵画だった。ぼくは驚嘆し、途方にくれてしまった。
その一週間後、ぼくは、東浩紀氏の思想誌『思想地図β3』の企画として、東氏、椹木野衣氏とともに震災後のアートについての鼎談に参加させていただくことになっていた。東氏と椹木氏はまさに『Murakami - Ego』展のオープニング・レセプションから帰国したばかりで、鼎談での話題もほとんどは『Murakami - Ego』展について、とりわけ《五百羅漢図》についてであった。
両氏の卓抜な分析によって、《五百羅漢図》は日米間の関係の産物である「オタク」というモチーフを超え、日本を含むアジア全体を射程に入れた東洋的芸術へと向かっていること、そして「現代美術」のなかの絵画の範疇におさまらない、歴史的「工芸品」のレベルに達していることなどが議論された。それまでの一週間に、呆然としながら、ぽつりぽつりと考えていたことが、言葉によって少しづつかたちを得ていくような、そんな時間だった。
鼎談を終えてほどなく、ぼくは「受け入れ」という言葉に思い当たり、迷うことなく本誌のテーマとしたのだった。
《五百羅漢図》は「悪い場所」としての日本を飛び越え、「アジア」という巨大な地盤の上に立ちあがっている。そしてその画面には、戦後の日本人がついぞまともに向き合うことのなかった「宗教」的なモチーフで満たされているのだ。震災への応答、というよりも、1000年に一度と言われたそのスケールに対峙するかのような作品である。
「受け入れ」というテーマは、そんな《五百羅漢図》の達成を前に驚嘆し、一度は言葉を失ったその後に、静かに浮かびあがった言葉だ。
戦後日本の「受け入れ」能力は極めて限定的なものだった。それは主として、戦後の日米関係に特化した「受け入れ」であり、「オタク」というモチーフはそのことをよく表している。しかし、地震と津波は「悪い場所」の起源である敗戦というトラウマよりも、はるかに深いところからやってきたのだ。これまでの「オタク」的モチーフは、震災によって吹き出したさまざまな記憶をその身に浴びて、容量オーバーでパンクしてしまった。
いまだ「悪い場所」としての日本に絡め取られているぼくたちの課題は、この国にアジアを、東洋的なものを、呼び寄せることなのではないか。つまりアジアにおける「受け入れ」の大国としてのヴィジョンを、新たに描くことではないか。本誌はそのための第一歩として作られた。
*
本誌の構成について説明しておこう。「受け入れ」特集は三部構成になっている。
第一部は、「受け入れ」の風景。
日本がアジアにおける「受け入れ」の国になったとしたら、いったいどんな風景になるだろうか、ということを描いてみようという試みである。
カオス*ラウンジを代表するアーティストである梅沢和木と藤城嘘には、ストレートに「風景画」を描いてもらった。これまでのオタク的なキャラクターによる作風は維持しつつも、巨大なゴミ捨て場のようにも、極楽浄土のようにも見えるような風景を、と依頼した。
続く北澤憲昭へのインタビューでは、北澤の主著である『眼の神殿』で明らかにされた「制度としての美術」という論点を、震災後の現在、今一度読み直してみようと思い、お伺いした。日本において「美術」が明治期に人工的につくられた制度であるならば、「美術」が「制度」であることを拒否するのではなく、むしろ積極的に現在の「アート」を人工的に構築していく必要があるのではないか、という話である。詳しくは本文にあたってもらうほかないが、「工芸とは拡張現実のことである」「複合的アーキテクチャとは桂離宮のようなものだ」といった北澤の言葉に象徴されるヴィジョンこそが、ぼくたちの貧しいデータベースを刺激し、アジア的なアートの入り口へ導いてくれるのだ。
カオス*ラウンジの中心作家である一輪社には、「受け入れ」というテーマで絵本を描いてもらうよう依頼した。すぐに一輪社から「空気」をモチーフにしたプロットが届き、ぼくは反射的にゴーサインを出した。この物語は未完であるが、近いうちに一冊の絵本として完全版をつくってみたいと思っている。
第二部は、「受け入れ」の園。
第一部の「風景」がヴィジュアルなモチーフだったのに対し、娯楽施設や商業施設といった、実際の遊戯・消費の場をモチーフとしている。
ディズニーランドやディズニーシーが、結果的にある種の理念や宗教観に近いものを体現しているように、大きな娯楽施設や商業施設はコンテンツビジネスの行き着く先であると同時に、優れた遊戯・消費の場は、必ず同時代の「アート」を内包する可能性を秘めている。ぼくたちは「受け入れ」のアートを考える上で重要な空間、場として、千葉の市川にある総合アミューズメントパーク「大慶園」を訪れることにした。同行してもらったのは、日本における「ゲーミフィケーション」紹介の第一人者である井上明人と、写真家の百頭たけしだ。
ちなみに、この取材にはもうひとつ隠れたテーマがある。それは、80年代から90年代にかけて栄えた「日本のキッチュ礼賛」のような趣味を乗り越える、というものだ。つまり宝島社の『VOW』や、都築響一の『珍日本紀行』や『TOKYO STYLE』といった興味深い仕事が、日本の宗教観や美術史観と結び付けられることなく、ただ「サブカル」として消費されるだけの受容や想像力を根本的に変えたいと思うのだ。これは「受け入れ」の国としての日本のアートを考える際に、避けて通ることのできない問題だと思う。
第二部の最後には、「受け入れ」というテーマで依頼した大島智子のイラストを掲載した。
第三部は、「受け入れ」の肖像。
「受け入れ」の国の人々は、いったいどんな人間だろうか。そのことを考えるきっかけとなったのは、中島岳志の著書『秋葉原事件——加藤智大の軌跡』だった。「ほんとうの承認」を求めて、ネットとリアルを彷徨った加藤智大の軌跡は、今の時代を生きる誰にとっても無関係ではない。
「受け入れ」の国であるためには、ネットとリアル双方が適度に重なり合ったコミュニティ、社会が不可欠であるが、そんな世の中で、ぼくたちの実存はどのようにケアされるのだろうか。中島岳志と気鋭のメディア評論家、濱野智史を招いた鼎談では、『秋葉原事件』で描かれた加藤の行動を分析しながら、次第にネット時代の「文学」の在り方についての議論になっていった。そして本誌最後を締めくくる福嶋亮大の論文は、震災後の文学についてである。
第三部の扉を飾るイラストは、みつごに依頼した。依頼の際には、すべてのキャラクターデータベースのメタレベルに立つ天使のようなキャラクターを、と伝えた。
最後に、本誌のデザインは大西正一である。大西とは以前から何度かカオス*ラウンジ関係の仕事をしており、そのデザイン力には絶対の信頼を置いていたが、今回の大西の仕事は突出して素晴らしいものだった。抽象的なテーマである上に、扱いにくい素材たちを、よくこれだけ統一感のあるデザインに落としこんでくれたものだと思う。本誌が一冊の「アートブック」としてかたちを得るために、大西の力は不可欠であった。
*
この国は、いつのころからかアートに何かを期待することをやめてしまった。
それは震災以後も変わらない。豊かな社会のためにアートは必要だ、アートは人を救う、という声のすぐ隣には、それをかき消すほどに大きく、アートなんて必要ない、アートなんて無意味だ、という声が鳴り響いている。ぼくたちはアーティストである以上、その声に向かって仕事を続けなければならない。
『GENDAI*ART』は、アートの本だ。
本特集が、この国おけるアートの力を、少しでも証明するものとなることを祈っている。
目次
「受け入れ」の国 黒瀬陽平
<1>
「受け入れ」の風景 ――「とある人類の超風景」
アートワーク:梅沢和木、藤城嘘
北澤憲昭インタビュー
絵本「AIR」 一輪社
<2>
「受け入れ」の園 ――大慶園探訪
「無国籍な風景から」井上明人×黒瀬陽平
写真:百頭たけし イラスト:大島智子
<3>
「受け入れ」の肖像
イラスト:みつご、一輪社
『秋葉原事件』という「バッドエンド」をめぐって
中島岳志×濱野智史×黒瀬陽平
「震災と文学」 福嶋亮大
奥付